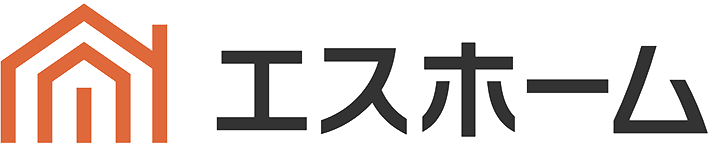Contents
お家づくりを考えるとき、「少しでも収納を増やしたい」と思われる方は多いのではないでしょうか。
2階建ての家の場合、その上にできる屋根裏空間を、収納としてうまく活用する方法があります。
この「小屋裏収納」は、限られたスペースを有効活用できる便利な場所。
ですが、その一方で、法的なルールや安全性の面からも注意が必要です。
今回は、小屋裏収納を取り入れる際に知っておいていただきたいポイントを、わかりやすくお伝えします。
面積のルール:下の階の半分まで
小屋裏収納を設ける場合、面積は下の階(直下階)の「2分の1以内」と定められています。
これは、建物の構造上の安全を守るための基準です。
収納といっても、本やアルバム、季節物の家電など、意外と重たいものを入れることも多いですよね。
そのため、小屋裏に過度に物を詰め込んでしまうと、地震などの際に建物へ大きな負荷がかかってしまいます。
安全に活用するためにも、「面積は半分まで」。これはとても大切な基準なのです。
また、屋根の傾斜でどうしても天井が低くなる部分も多く、実際に使いやすいスペースは限られます。
無理なく、無駄なく。ちょうどよい広さで計画するのがポイントです。

天井の高さは「1.4mまで」
天井の高さについてもルールがあります。
小屋裏収納は、「高さ1.4m以下」にしなければなりません。
1.4mというと、小学生なら立って歩ける高さですが、大人だと腰をかがめないと動けないくらい。
ちょっとした物の出し入れなら問題ありませんが、長時間過ごすのは難しい空間です。
この制限には、「ここを居室として使わないでくださいね」という意味も込められています。
実際、もしもこの空間を寝室のように使っていたとしたら――
火事や災害のとき、助けに行くのが難しく、非常に危険です。
たとえば3階建ての家では、万が一の火災時に備えて「突入口(とつにゅうこう)」の設置が義務付けられていますが、2階建ての小屋裏収納にはそうした義務はありません。
安心して暮らすためにも、小屋裏収納はあくまで「収納」。無理のない使い方を心がけましょう。
本来の使い方は「収納」です
あらためてお伝えすると、小屋裏収納は名前の通り「収納」として認められた空間です。
ところが中には、書斎や子ども部屋として使っているお家もあるようです。
住宅展示場で、小屋裏収納を「秘密基地のような子ども部屋」にしている例を見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。
実は、そうした使い方は建築基準法の趣旨から外れており、本来は認められていないことです。
もちろん、お引き渡し後の使い方はご家族次第ではありますが、万が一に備えるためにも、やはり収納としての使い方をおすすめします。

平屋の屋根裏収納は、少し自由度が高くなります
最近人気の「平屋」。階段がないことで生活動線がラクになり、年齢を重ねても暮らしやすいと注目されています。
その一方で、2階がないために収納スペースが足りなくなってしまう、というお悩みも。
そこで、平屋の屋根裏に収納を設けたいというご希望をいただくことがあります。
この場合は、2階扱いになるため、小屋裏収納に比べて面積や天井高さの制限はゆるやかになります。
階段もつけられますし、天井を高く取ることも可能です。
使いやすさを優先して、しっかり計画しておくと、ぐっと快適な空間になりますよ。
「階段をつけたい」――その夢は叶うのか?
小屋裏収納といえば、天井から降ろす「はしご」が一般的です。
ですが、これがちょっと曲者。
はしごは、上り下りが不安定になりがちですし、荷物を抱えての移動には危険が伴います。
特に女性やご年配の方には、負担が大きいものです。
「階段をつけられればいいのに…」という声をよくいただきますが、実は法律上、階段を設けると「3階」とみなされることがあり、建物全体に厳しい規制がかかる可能性も。
ただし、自治体によって判断が分かれる部分でもあるため、まずはお住まいの市役所や建築指導課に相談してみるのが安心です。
栃木県内の多くの市町村では、小屋裏収納に階段をつけることが認められています。

おわりに:ルールを知れば、安心して活用できる
小屋裏収納は、うまく使えばとても便利なスペースになります。
大切なのは、「どう作るか」よりも「どう使うか」。
法律や安全面の制限をきちんと理解したうえで、あなたの暮らしに合った形で取り入れることが何より大切です。
信頼できる建築士さんと一緒に、あなたにぴったりの小屋裏収納を考えてみませんか?
「収納の夢」、叶えましょう!