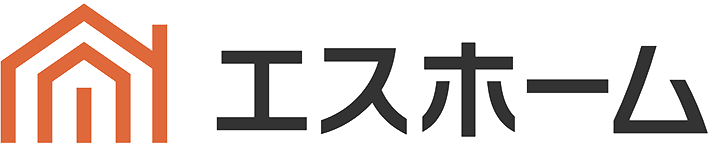もう2年半前になるのでしょうか。新建ハウジングの企画で「ホームズ君」の使い方と構造計算の許容応力度計算を教わりました。
その先生が鈴木先生。とても気さくな方で一生懸命教えてくれました。
鈴木先生に教わった方法は、私の家にも応用版として採用しています。
今回、特別に鈴木先生の現場を見せていただけるという事で、新潟まで行ってきました!
坂井東邸
まずは、坂井東邸。
真ん中あたりで話しているのが鈴木さんです。

外壁は、最近多い木仕上げです。
通常よりも基礎が高いのも特徴です。
鈴木さんのお家の特徴の一つが、30坪以下ということ。
そのコンパクトさでもしっかりと生活できるように考えてあります。

2階は、広々とした設計です。

構造計算をすると、柱や梁を入れたり、入れなかったっり調整することができます。どのような事かというと、広い空間を作ったり天井の高さを調整したりもしやすくなります。

構造の高さはとっても低いのですが、小屋裏を天井としているので、圧迫感は感じません。2階の天井を下げると外観がカッコよくなるので、このような工法も良いですね。
関屋近衛町邸
こちらは、外壁の下地を見ることができました!
気密性能は、当然のように0.1cm/m2です。
さすがです。

外部に貼ってある木(胴縁と呼びます)にも特徴があります。通常は縦か横の一方向なのですが、縦と横に貼ってあります。それだけ外壁の通気も取りやすくなります。
屋内に入ると、そこにも窓がありました!
これは、写真を撮っている部屋は風除室のようになるのだそうです。その部分は断熱もせずに外部として考えます。この掃き出し窓が、実質的な入り口になります。

1階の内部がこちら。
注目は、2回の床です。一般的には横にも針を入れるのですが、鈴木さんは入れていません。これは断面欠損という、梁を弱くする部分を無くす方法です。床なりが心配なので横にも入れるのですが、特に問題ないとのことでした。

基礎下がこちらです。
基礎は通常よりも高さを上げています。地盤面から1m!
通常は40cmなので、60cmも高くしています。その分、物置に利用することができるようになっています。すでに職人さんが利用していました。

床面積は小さいですが、このような利用の仕方をしているので収納料はたっぷりと稼いでいます。
窪田町
基礎工事の現場も見せていただきました!
さすが、基礎高が1mもあるので、パネルも高いですね。

一般的に、基礎は下の部分(耐圧板)と立ち上がりを分けて2回打つのですが、鈴木さんは1回で打つのだそうです。
これだけの基礎を1回で打つのはなかなか大変なそうで、コンクリートの重みで枠が変形してしまうこともあるのだとか。

小雨の寒い中でしたが、鈴木先生は熱心に教えてくださりました!
次回は、鈴木先生のご自宅を紹介します!