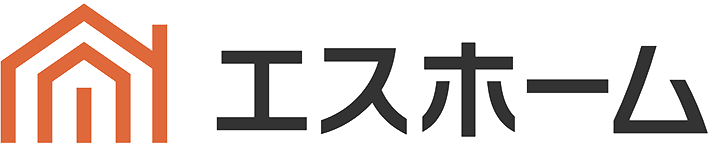Contents
こんにちは。一級建築士の西村です。
今日は、少し怖いけれどとても大切な「竜巻(たつまき)」について、そして家づくりや土地選びでできる備えについて、やさしくお話しします。
「栃木県内だから竜巻は関係ないでしょう。」
と思われるかもしれませんが、過去には栃木県内でも竜巻が発生して被害を及ぼしています。
先日、茨城県つくば市で実際に竜巻が発生し、多くの建物が被害を受けました。その調査報告が2025年10月3日に国土交通省から発表されましたので、その資料を元に考えたいと思います。
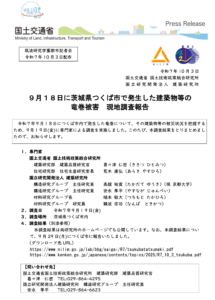
竜巻ってなに?
竜巻は、とても強い回転をともなった風の柱です。
空気の流れがねじれてクルクルと回るうちに、地面まで達すると竜巻になります。まるで巨大なコマが地面に降りてきて、暴れながら進んでいくようなイメージです。
竜巻の強さは、アメリカで使われている「藤田スケール(Fスケール)」を日本用に直した「日本版改良藤田スケール(JEF)」で表します。
今回つくば市で発生した竜巻は「JEF1」に分類され、最大風速はおよそ45m/sと推定されました。これは、時速にすると160km以上!
気象庁によると、「屋根瓦が飛び、ガラス窓が割れる。ビニールハウスの被害甚大。根の弱い木は倒れ、強い木は幹が折れたりする。走っている自動車が横風を受けると、道から吹きおとされる。」くらいの強さです。
ただし、竜巻は台風のように広範囲で被害を及ぼすわけではありません。ここでいう広範囲とは、竜巻は地面の辺りに来ると幅が狭くなります。そのため、竜巻の足元あたりは10〜20mの幅もないくらいになり、被害はその辺りにしか出ません。
表現は悪いですが、酔っ払いが千鳥足で歩いていてその周りだけ被害をおよぼす、そのように説明した方がわかりやすいかもしれません。
不幸にも竜巻に当たってしまったお家の被害は大きいけれど、隣のお家は無傷、ということになるのです。

つくば市で起きた竜巻の被害
2025年9月18日、つくば市周辺では前線の南下によって空気の状態がとても不安定になり、活発な積乱雲が次々に発生しました。そのうちの一つが花室(はなむろ)という地域を通過したとき、竜巻が発生しました。
調査によると、次のような被害が見られました。
- 2階建ての建物が倒壊し、1階部分がつぶれるように壊れてしまった
- 屋根瓦が吹き飛ばされた
- 外壁の一部がはがれた
- カーポート(車庫)の屋根がめくれた
- シャッターが外れた
- 物置が飛ばされた
- 看板に飛来物がぶつかって壊れた
…など、住宅だけでなく周辺設備にも大きな被害が及びました。
特に倒壊した住宅は、1985〜1990年ごろに建てられた築35〜40年の建物でした。1階部分が「層崩壊(そうほうかい)」と呼ばれる形で押しつぶされ、2階部分がそのまま地面に落ちてしまうという、非常に危険な壊れ方をしていました。
また、屋根瓦には釘やネジなどのしっかりとした固定が見られず、強風で簡単に飛ばされてしまったこともわかっています。

木造住宅は竜巻に弱いの?
「木の家は竜巻で壊れやすいのでは?」と心配される方も多いと思います。確かに、木造住宅は鉄筋コンクリート造や鉄骨造に比べて軽いため、強風で被害を受けやすい面があります。ですが、これは「古い建物」や「施工の精度が低い建物」で起こりやすい現象です。
現在の建築基準や施工技術をしっかりと守って建てられた木造住宅は、適切な補強や部材の固定によって、竜巻に対しても大きく耐える力を持たせることができます。
家づくりでできる竜巻対策
屋根や外装材の固定をしっかりと
今回の調査でも、瓦が釘やネジでしっかり留められていなかったことで、大きな被害が広がったことが確認されました。屋根材は、強風による「めくれ」を防ぐため、金具やネジを使ってしっかりと固定することが基本です。
特に瓦については、以前は釘留などしていないお家が多かったようです。現在では、全部の瓦を釘で止める工法が一般的となっています。
構造的な一体化で「家全体で風に立ち向かう」
1階の壁が少なく開口部(窓やドア)が多いと、風の力で潰れてしまう危険があります。これを防ぐには、耐力壁をバランスよく配置し、上下階をしっかりつなぐ金物を使うことが大切です。
また、屋根と柱、柱と土台をきちんと金具で緊結(しっかり留める)ことで、風の力が建物全体にうまく流れるようにできます。いわば「家全体で風に立ち向かう」構造を作るイメージです。
付属物の飛散対策も忘れずに
シャッターや物置など、家の付属物も強風時には飛ばされやすく、人や建物に二次的な被害を与えることがあります。これらも日ごろから点検し、しっかり固定することが大切です。
お家にシャッターが付いていて、なおかつ閉まっていれば効果ありますが、ガラスのみの場合には割れてしまい屋内に被害が出る可能性が高くなります。
土地選びで気をつけたいこと
実は、家を建てる「土地選び」の段階でも、竜巻対策を考えることができます。
竜巻は「積乱雲ができやすい場所」に発生する傾向があります。具体的には、広い田畑や河川沿いなど風の通り道になりやすい平地、大きな建物が少なく風が遮られにくい場所、温かい空気と冷たい空気がぶつかりやすい地形などは注意が必要です。
以前栃木県内で起こった竜巻の現場を見に行ったのですが、街と田畑や林の間あたりで起きているように感じました。温度差が起きそうな場所ですよね。
もちろん、土地だけで竜巻を完全に防ぐことはできませんが、被害が集中しやすい地形を知っておくことで、リスクを減らす選択ができます。
また、周囲に大きな建物や防風林などがある土地では、風の勢いが少し弱まることもあります。自治体のハザードマップや気象庁の突風事例データをチェックすることも有効です。過去に突風や竜巻が発生した地域では、将来も同じような現象が起こる可能性があります。

まとめ 〜家と家族を守るために〜
竜巻は、発生する頻度こそ地震や台風ほど多くありませんが、一度発生すると非常に強い力で家や周囲の環境を壊してしまいます。
しかし、正しい知識と備えがあれば、被害を最小限に抑えることはできます。
今回のつくば市の事例では、古い建物での構造的な弱さや屋根瓦の固定不足が大きな被害の原因になっていました。
これから家を建てる方は、最新の建築基準をしっかり守り、構造・固定・配置を丁寧に計画すること。そして土地選びの段階からリスクを考えることが、家族を守る第一歩になります。
私たち建築士は、「安心して長く住める家」をつくるために、目に見えない部分こそ大切にしています。
家づくりを考えるとき、ぜひ「竜巻」という自然の力にも、少し目を向けてみてください。それが、家族と未来を守る大きな力になります。
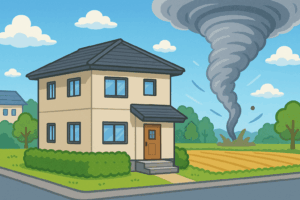
参考文献:
国土交通省 国土技術政策総合研究所
国立研究開発法人 建築研究所
「令和7年9月18日 茨城県つくば市で発生した建築物等の竜巻被害 現地調査報告」